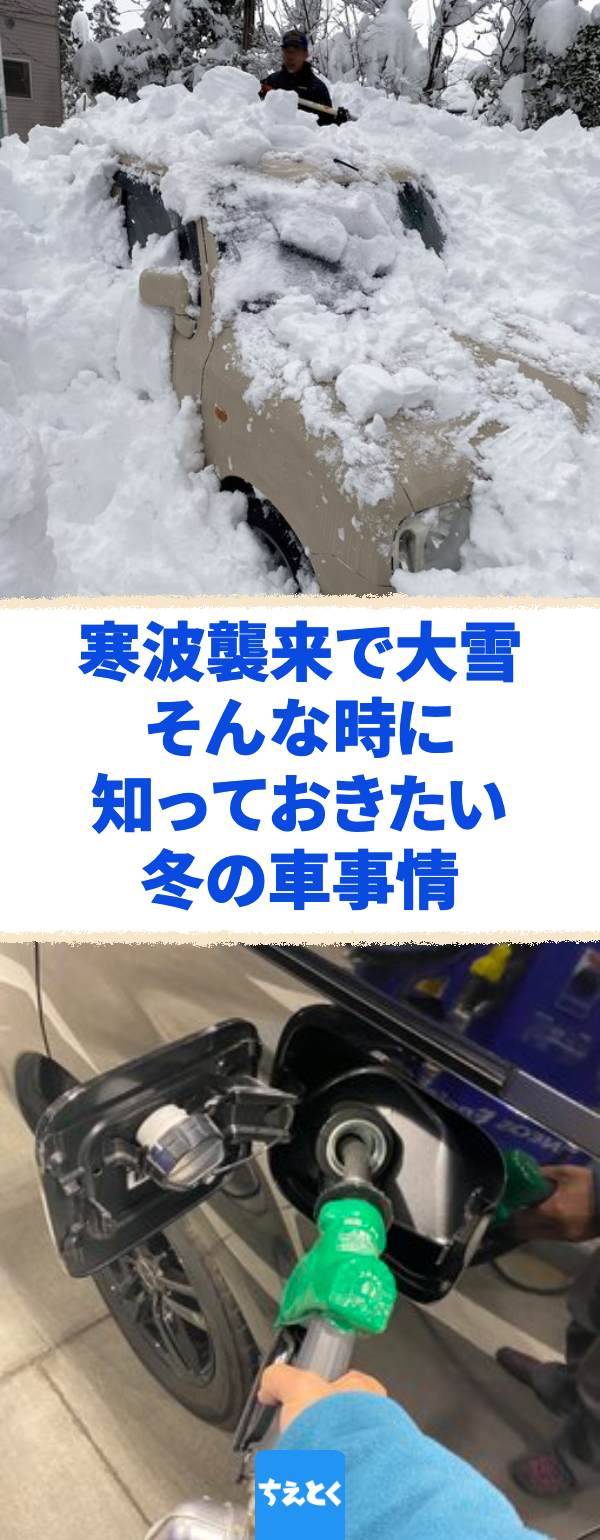その他の豆知識
寒波襲来で大雪|そんな時に知っておきたい車についての注意点
年末年始から年明けにかけて、毎年降る大雪。昨年2021年の年明けは、寒波に見舞われ厳しい寒さが続いた日本列島で、日本海側の多いところでは平年の3倍の量の降雪を記録しました。
豪雪地帯にお住まいの方々も雪には慣れていると言えど、短期間で降った想定外の雪の量に驚いている様子。
豪雪地帯に生まれ育った両親も驚きの大雪がふりました❄️ pic.twitter.com/IGTgoEeiDN
— サクライ父@9ヶ月育休取得完了 (@HGkXbA7pTXc2Bvj) January 10, 2021
駐車しておいた車が雪で埋もれてしまうという写真や雪山の中から掘り起こすという光景にも目を見張ります。
連日の大雪!今日は社員寮にて車を掘り起こす作業です!#阿賀野市 #村杉温泉 pic.twitter.com/PU5Qr0Lrhj
— 風雅の宿 長生館 (@chouseikan1) January 10, 2021
新潟市雪やばすぎる(´゚ω゚`)
車埋まってるし、私の車だせない pic.twitter.com/TqEeFTX5ad— あーたそ (@ata819) January 9, 2021
しかし、実は一見普通に車が駐車されているように見えますが、そこには雪国の工夫が。そこで今回は、降雪時や氷点下で気をつけたい車の注意点をご紹介します。普段雪が少ない地域ではあまり知られてない、冬の車事情。知っておけば、いざという時にきっと役立つはずです。
1. 駐車時の注意
・駐車時にパーキングブレーキ(サイドブレーキ)をかけない。
普段車を停止して駐車する時、AT車でもマニュアル車でもサイドブレーキを必ず使います。しかし、大雪の場合ではサイドブレーキワイヤーにこびりついた雪が凍って、びくとも動かなくなります。寒冷地ではサイドブレーキを使わず、AT車の場合はシフトポジションをPに、MT車の場合は1速(下り坂ではリバース)に入れて駐車し、そして輪留めを車体の対角線上に位置する前後2箇所に設置し車を固定します。
-12℃の雪から車を掘り起こし安心してうっかりサイドブレーキをかけブレーキが凍り付いた。雪国育ちはご存じかな。これは雪山ダメダメ行動の一つです。これは「マイナス気温の世界で車が動けない」しかも「自然解凍するまでは動けない」ことを意味します。が、幸運にもブレーキを解除できて無事下山 pic.twitter.com/F0X3XexCWc
— go10@スキーシーズン (@Goo10) December 31, 2020
最近では電動式パーキングブレーキシステムを搭載した車もあり、エンジンを停止させると自動的にパーキングブレーキが作動する仕組みになっているので、その場合は予め取扱説明書を参照し、自動的にパーキングブレーキが作動しないように対処をします。
・降雪時の駐車場所に注意
寒冷地での駐車方法の基本は、なるべく平坦な場所を選ぶこと、そして軒下や樹木の下、また吹き溜りになるような角や奥には車を駐車しないでください。吹き溜まりになる場所では他よりも雪が大量に積ったり、樹木や軒下では落雪で車が損傷するおそれがあります。
職場で指定されてた駐車場に車を停めてたんだけど、ここ数日の大雪で溜まりに溜まった屋根の雪が全て落ちてきて、車の天井とフロントガラスが潰れてワイパーも折れた\(^o^)/ pic.twitter.com/bS8hwZRoH1
— es (@es_atlf) January 28, 2019
2. 凍結対策
・フロントガラス
フロントガラスの凍結予防や凍結した際の対策を以前ちえとくで紹介しましたが、大量の降雪によりフロントガラスに雪が積もっていた場合は、解氷スプレーと樹脂製のスクレーパーを使って雪を除去します。そして雪を取り除いたら、そのまま走り出すと極寒の空気に勢いよく当たったフロントガラスがサーっと凍りついてしまうため、デフロスターでヒーターの温風をフロントガラスに当て、凍りつかない程度に温めてから車を走らせるようにしてください。
・鍵穴
また、フロントガラスの凍結予防や対策の他にも、吹雪くような天候の場合は鍵穴の凍結にも注意が必要です。最近はキーレスエントリーやスマートキーが主流で鍵穴にキーを差し込んで施解錠する機会はほとんどないと言えますが、バッテリー上がりなどのトラブル時のメカニカルキーと呼ばれる、差し込むタイプの一般的な鍵が搭載されており、この鍵を使ってドアを開けることになります。
万が一の時のため、鍵穴にはあらかじめ解氷スプレーを吹きかけておくようにします。そして電動リモコンミラーも、作動不良を起こし故障の原因となる可能性もあるので畳まずに、そのままにしておきます。また自動格納式のドアミラー装備車も、勝手に動かないように設定する事が可能です。
これは一般的に知られていると思いますが、この他にも氷点下ではワイパーが凍結したフロントガラスに固着してしまうことがあります。強引に剥がすと、ブレード部分がちぎれて使用できなくなることも。車を離れる際は、ワイパーを立てておくようにします。
うちの車が大変なことに?
明日の朝にはもっと大変なことになりそう??
早く雪やまないかなぁ??
#新潟市#大雪 pic.twitter.com/MRrPMGjuVa— Yumisora17 (@Wp0ONarB75nRegI) January 9, 2021
・ウィンドウォッシャー液や冷却水の凍結対策
極端な気温低下により、ウインドウウオッシャー液や冷却水なども凍結する場合が。そのため、もし寒冷地に入る前は、ウインドウウオッシャー液を不凍タイプにする、また冷却水は取扱説明書などで確認し、外気温に合わせながら必要な濃度に調整をするようにします。
・ディーゼル車用の燃料の凍結対策
ディーゼル車の燃料として使われる軽油は、5種類に分類され、季節や地域に合わせて販売されています。寒冷地へ出向く前に満タンにしてから、現地の気温の低い駐車場などに停めておくと、タンク内の軽油が冷えてエンジンがかからなくなることもあります。ディーゼル車の場合は、道中で寒冷地用の軽油を足して凍結対策をするようにします。なお、今年3月末まで予定されている寒冷地用の軽油の販売場所はこちらからご覧になれます。
3号軽油給油完了⛽️
軽油のお車の方は、寒冷地に行かれる場合、凍結防止の為に、3号軽油をタンクの半分は入れるように意識しましょう。軽油は地域で価格差が少ないのも魅力✨#デリカD5 pic.twitter.com/JF6EmErctE
— ばもくん(キャンプ×料理×温泉) (@vamo_TakaIke) January 2, 2021
3. 走行時、LEDライトなら要注意
車のヘッドライトに省電力のLEDライトが装備されていたり、ハロゲンバルブから新車検対応に対応し、実用的な明るさを獲得した市販のLEDバルブに組み替えている人も多いと思います。しかし、降雪地域を走る場合や夜間の走行で雪が降り出した場合はLEDライトの場合は注意が必要です。LEDライトは従来のハロゲンライトに比べてライト内に熱がこもらないため、降雪時にはレンズに付着した雪が溶けずにビッシリ覆われやすく、走行中にだんだんと付着した雪によって光が遮られてしまうのです。このため、雪道の夜間走行時は定期的に停車してヘッドライトの雪を落とすようにしてください。
やっぱり豪雪地帯にLEDライトは向かないよ…ワイの車はブレーキランプのところが解けてるけど、隣のフィットさん(LED)は完全に雪かぶってる。ヘッドライトはなおさら。さらにヘッドライトはハロゲンの淡い黄色の方が雪の中で気づかれやすいし。
LEDやめろとは言わんが熱線入れるとかできないのかな… pic.twitter.com/mnrzmF0znL
— 海洋五所(はいやん) (@haiyangwusuo16) December 16, 2020
寒波が襲来することが多い1月から2月にかけて、降雪時や路面凍結時のクルマの扱い、乗り方など、通常とは違った安全対策をしっかり取っていきたいですね。
また、積もった大雪に雨が降り、雪の重みが増すことによる被害や、冠水などが懸念されます。通常なら影響が出るような雨でなくても、道路脇に多くの雪が残っていることで排水が滞り、雪どけ水が加わって道路冠水が発生することがあります。仮に1立法メートル当たりの新雪を100kgとすると、10mmの雨が降るだけで、1割重さが増すと言われています。カーポートやビニールハウス等の構造物の倒壊危険性がさらに高まることになりますので、大雪後は周囲に危険な所はないか確認をし、くれぐれも注意するようにしてください。
以前紹介した、大雪の際に車に残されてしまった場合の対処法も併せてご覧ください。
プレビュー画像:©︎Twitter/ata819